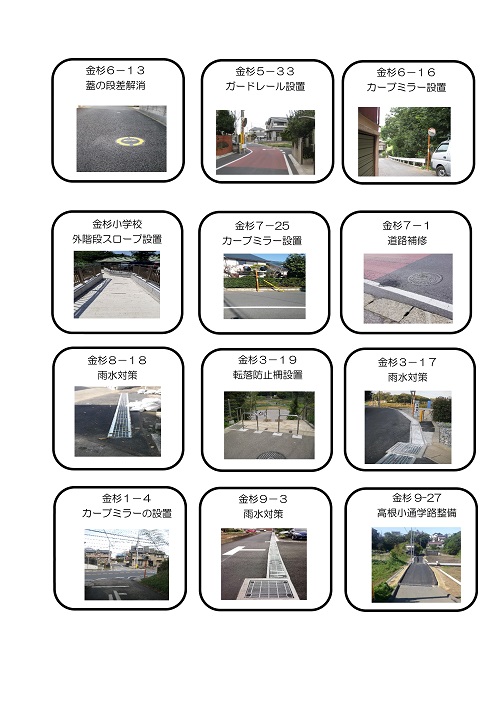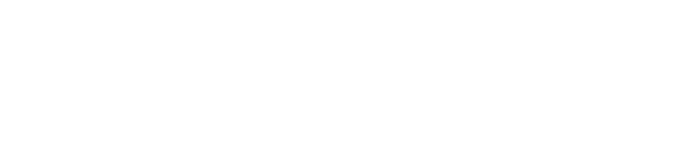14署目となる「船橋市東消防署古和釜分署・船橋市消防訓練センター」が、4月にオープンします。
今日は、内覧会が開催され、参加しました。
平成29年度から2カ年計画で、建設が始まり完成しました。
出動準備室です。3交代なので、防護服などが一式が掛けられるようになっていて、回転式で3面あります。
3交代なので、仮眠室のベッドの下は、3人分の物入となっていました。
これは、出動から戻った後の、ホースを干す場所だそうです。汚れを落とした後、かけて干すのだそうです。
1階に、仮眠室や出動準備室があるのは、市内初だそうです。他の署では、2階にありますが、ここでは降りる手間がなく、準備が整い次第、すぐに、出動ができます。
訓練棟C棟は、救出活動を訓練しますが、迷路室があり、暗闇の中での訓練も行うそうです。
訓練棟B棟は、火災訓練で、実火災訓練室がありました。
はしご車などによる高所救出訓練、実際に煙を使用した火災想定訓練、迷路室等を使用した人命検索訓練などの他、今まで行えなかった大規模な訓練ができるようになりました。
また、町会・自治会や自主防災組織、小・中学生の体験型訓練もできます。
訓練センターを大いに活用し、消防職団員の皆様の災害対応能力が向上することを期待するものです。