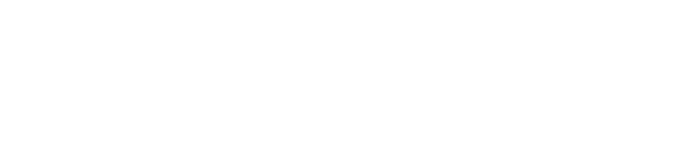令和7年第2回定例会の一般質問です。

はしもと・・・本市では、放課後の居場所として欠かせないのが、放課後ルームと放課後子ども教室「ふなっこ」があります。
保育園の待機がなかなか減少しない現状を考えると、当然、ルームの利用者も多く待機があるのもうなずけます。
「ふなっこ」を始めた当初は、ルームからの利用を変更するのではないかと期待したものですが、案外そうではなかったようです。
ルームでは5時に迎えに来るのが約半数だと聞きます。
方や有料であり、方や無料であるにも関わらず、なぜ、ルームの利用者が多いのでしょうか。
利用している子どもに聞いてみました。
「最初はルーム、でもふなっこでもいいかなと思い、ルームをやめたが、ふなっこは、友達がいない時がある。ルームに行けば、必ず友達がいるので安心。」親に確認すると「大抵5時にお迎えに行かれるので、ふなっこでもいいが、渋滞などで遅れた時は、心配なので、ルームにしている」とのことでした。

令和6年8月のふなっこ利用者アンケートの結果を見てみました。
好意的な意見が多数をしめていましたが、中には、改善が必要な意見もありました。
ルームとふなっこを比べてみると、1人当たりの面積基準が決まっているのはルーム、ふなっこは、密集していても面積基準がない。
5時のお迎え、ルームは、過ぎても大丈夫、ふなっこは、5時で外に出されてしまう。
また、暗くなるのが早い時期には、4時頃に帰されてしまう。
ふなっこは、下駄箱がないため、学校での上履きを、その都度持ち帰り、次の日に学校へ持っていく。
空気清浄機があるのは、ルーム。
夏休み中のお弁当注文ができるのは、ルーム、ふなっこは、お弁当持参、クーラーボックスがないため、保管に困っている。
など、様々な声がありました。
また、ふなっこでは、職員をはじめとした大人の対応やキツイ言葉が怖かったりして、利用するのをやめた。との回答が多かったのには、驚きました。
中には、職員同士の雑談に花が咲き、話かけられずにいた。体罰に近い行為もあった。ともありました。
中には、有料でもいいので、課外授業的なものや習い事のようなものができると嬉しい。
公民館のサークル等で、講師をしている方にお願いして、体験活動がしたい、地域の方との交流にもなるのでは。と言った声もありました。
また、ルームでは、個別に相談を頂いていますが、例えば、主任支援員をやったが、自分には無理と感じ、支援員を要望。
なり手がないため、引き続きやってほしいと、担当課から言われた。
支援員から補助員に対するパワハラもあります。
その逆で、子ども達の前で、支援員に対し、わざとわかるような嫌がらせをする補助員もいます。
ルームの、人手不足はなかなか解消しません。
このような声がある中で、放課後の子どもの居場所として適切なのか、関わる大人の資質はどうなのか。考えざるをえません。
そこで伺いますが、アンケート結果、私たちに届いている相談などを通してどのように考えているのか、それぞれの担当課にお伺いいたします。

生涯学習部長・・・昨年8月に実施したアンケートは、「船っ子教室のご利用に関するアンケート」と称して、放課後子ども教室の運営に関するご意見を把握し、現場職員に対して指導することを目的として実施したものです。
アンケートの自由記載欄には、ご指摘のような職員への苦情、設備面の不足等、様々なご意見・ご要望をいただいており、運営上の課題と認識しています。
職員への苦情や誤った運用ルールについては、各放課後子ども教室のコーディネーターとの面談において共有し、指導したところです。
併せて、毎年、職員研修を実施し、質の向上に努めております。
今後も、利用者の意見を真摯に受け止め、安心・安全な居場所として放課後子ども教室をご利用いただけるよう、内容の充実を図ってまいります。

子ども家庭部長・・・放課後ルーム職員にかかる問題につきましては、その内容により園長だけでなく、所属課職員も各放課後ルームに赴き、状況確認や指導を行っているところです。
さらに、全職員を対象とした職場環境の改善を目的とした職場アンケートを実施するなど、放課後ルーム職員の意見を聞いているところです。
その中で、議員ご案内のような要望や相談がありましたので、今後も引き続き、放課後ルームに従事する職員の意見を聞きながら、働きやすい環境づくりに努めてまいります。
また、例年実施している支援員研修に加えて、今年度から新たに補助員研修も開始するなど、職員の質の向上に向けて取り組んでいます。
今後も、放課後ルームに通っている子ども達が、より一層安心して楽しく過ごせるよう、放課後ルーム全職員の資質向上に努めてまいります。

はしもと・・・ふなっこでは、運営上の課題と認識している。
ルームでは、働きやすい職場づくりなど、いずれにしても、子ども達の放課後の居場所を、見直さなければならない時期に来ていると思います。
このような中、全国各地で、ルームとふなっこを合体させたアフタースクールの取り組みが進んでいます。
5月に会派で千葉市に伺い、勉強をさせていただきました。

千葉市における、アフタースクールとは、「小学校の放課後において、保護者の就労状況等にかかわらず、希望するすべての児童に『安全・安心な居場所』と『多様な体験・活動の機会』を提供するものです。」とあります。
いわゆる、放課後ルームと放課後子ども教室を一体化し、全ての子どもが安心して過ごせる場所です。
昼の部と夜の部が設けられ、授業終了後から17時までが昼の部、夜の部は、17時から19時までで、保護者が迎えに来られる方を限定としています。
利用料金は、一般世帯、低所得世帯、生活保護受給世帯を含む住民税非課税世帯の3区分があります。
多様な体験・活動の機会となるプログラムがあり、体験プログラムでは、地域住民や保護者などの参画も得ながら、例えば、工作や制作、昔遊び、英語、運動など、原則無料で、週2回程度。継続プログラムでは、利用料金とは別に参加費が必要ですが、習い事に相当する継続的な学びとして、サッカー、ダンス、体操、プログラミング、科学実験など、週1~2回程度。提供されています。
令和14年度までに98校すべての小学校に導入とのこと。
この他にも、柏市が、今年度、市長部局と教育委員会が一体となり、教育委員会の中にアフタースクール課を設置し、条例の制定や取り組みなど、放課後の子ども達に、安全・安心な居場所について、取り組んでいます。
また、板橋区・大田区・さいたま市なども取り組んでいます。
今年度、子どもの居場所について協議しているとのことですが、市長はどのような思いから、協議をはじめ、どの様な事を協議しているのか、アフタースクールについても検討しているのか、松戸市長に伺いいたします。

市長・・・まず、庁内の協議会についてご答弁させていただきます。
子どもに関する施策につきましては、これまで教育委員会そしてまた福祉部局それぞれが自分たちの組織の中で、それぞれの立場でいろいろ取り組みをすすめてきました。
今、議員がご質問の中にもあったように変化をしてきており、これからどういった形がよいのか、子ども達のそれぞれの所管の立場から見た子ども達ではなく、子ども達から見たそれぞれの必要なものは何なのかっていうことをやっていくべきだということで、これが、教育委員会そして福祉部門、それぞれの他所管の方で意見が一致したことを受けて、今年の4月に教育委員会と相談しながら、子どもの居場所作りに関する庁内協議会を立ち上げました。
協議会では、私を含めて教育長、副市長、福祉局関係部長のもとで、子どもの居場所について、本市の子ども達に何ができるのか、そして、その方針、関連する情報や課題を共有して、議論をしていこうということで、スタートしております。
先日、第2回の協議会を行いましたが、その時のテーマとしては、①放課後の子ども達の居場所について、②不登校となっている児童や保護者への支援、③学校始業前の子どもの居場所、この3点について協議を行いました。
これらのテーマについては、引き続き取り組んでいきますが、協議会では、それぞれ市全体の中での観点、そして強みを活かすことができる、重層的な協議、そして検討を行う。
実際に私もやり取りしましたが、今までとは違った観点での意見がかなり多く交わされたというふうに考えています。
今後についても、課題への共通認識を持って、子ども達を育む教育の環境整備と、子ども達の居場所作りについての推進に繋げていきたいと考えております。
そして、アフタースクールに関してでありますが、議員のご紹介のあった、千葉市と柏市の事例ですが、私どもも把握しております。
それぞれの所管の方で、色々と確認をしていますが、その中で、放課後ルーム、船っ子教室とは少し異なる部分も当然あります。
本市でいう放課後ルームと、船っ子教室の一体運営という面では、参考になるところが当然ありますので、千葉市と柏市の運営形態が船橋市に馴染んでいくのか、また、参考にできる内容があるのかどうか、今、検討を進めているところもあります。
一体的な運営については、人員面や施設面など既存資源の有効活用が見込まれる一方で、それ以外の課題も当然あります。
その実現の可能性も含めて、船橋の放課後の子ども達の居場所作りのためにはどのような事業の在り方や体制がいいのか、この協議会で、引き続き丁寧に検討を重ねていきたいと思いますし、より良いものを生み出していきたいと考えています。
はしもと・・・この件に関しては、今後も取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。