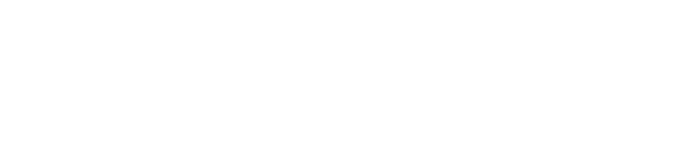先日、友人から「補聴器購入費は、医療費控除の対象になりますか?」との質問がありました。
メガネの場合は、眼科で検査してもらい、処方箋があれば、医療費控除の対象になることは知っていました。
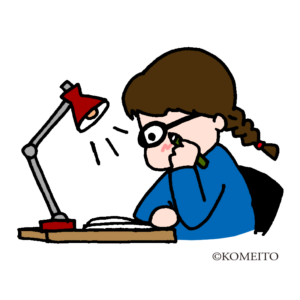
14年前に白内障の手術をしてから、人生初のメガネを使用することになり、処方箋を持って、メガネを購入し、その時の領収書で、医療費控除をおこないました。
補聴器について、市民税課に確認したところ、「医師の文言があれば、処方箋でなくても、医療費控除の対象になる」と、教えてもらい、早速友人にお伝えしました。
また、購入するときは、必ず、耳鼻科で診察してもらい、できれば、補聴器専門医がいる耳鼻科が良いことも、お伝えすると、友人からは「いきなり補聴器専門店で購入ではなく、補聴器専門医のいる耳鼻科に受診することがポイントなのですね」と。
ただし、医療費控除の対象になりますが、あくまでも所得税を払っていることが条件です。
年末調整や確定申告は、収入に対する税金に対し、控除するものです。

また、令和6年第2回定例会で、補聴器購入費助成について質問をしましたので、以下をご覧ください。

はしもと・・・補聴器購入費助成についてお伺いをいたします。
年齢とともに聴力が衰える加齢性難聴に悩む高齢者に補聴器の購入費助成と難聴の早期発見、購入前の相談からアフターケアまでの切れ目のない支援が重要です。
本市では、聴力低下により、非課税世帯で2万円までの助成はありますが、以前から金額を上げてほしいとお願いをしておりますけれども、担当課からは比較的軽度なうちに早い段階で補聴器を利用してほしいと言われておりますが、実際には最初から高額の物を購入する方が増えております。それはなぜなのでしょうか。
先月、医師会の会長(耳鼻咽喉科医)のところに行ってお話を伺ってまいりました。
眼鏡は検査をしてから購入をする。
補聴器は使いながら調整をしていくので、自分の耳に合うのに数か月かかると言われておりました。
補聴器をつけることで、すぐに音がはっきりと聞こえるだろうと思いがちですが、補聴器は眼鏡と違い、つけるだけではなく音を聞き取るトレーニングが必要なのだそうです。
安い物を購入しても耳に合わず、すぐに外してしまう方がいると聞きました。
そこでお伺いしますが、ここ数年の助成件数と実際の購入金額の状況を教えていただきたいと思います。
健康・高齢部長・・・高齢者への補聴器の助成につきまして、直近3年間の助成件数でございますが、令和元年度が104件、令和2年度が78件、令和3年度が92件となっております。
また、実際の購入金額の状況につきましては、年度により異なりますが、最低で2万円前後、最高で、令和3年度は114万円という例が1件ございますが、おおむね70万程度という状況でございまして、平均額は18万円前後となっております。
そのうち、おおむね1割程度の方は購入金額が5万円未満となってございます。

はしもと・・・難聴は認知症の最大の原因とも言われております。
聴力が低下をすると相手の声が聞き取れず、話の内容もよく分からなくなります。
本人にとってはとてもつらいものですけれども、実は周囲の人も同じことを何度も繰り返したり大きな声で話をしなければならず、ストレスとなってしまうことがあります。
そうすると、本人は周囲の人に負担をかけている自分に気がつき、やがて話をしなくなります。
難聴のためにコミュニケーションがうまくいかなくなると、人との会話を避けるようになり、次第に気分が落ち込んで憂鬱な気分になり、外に出るのが嫌になったり、また、社会的にも孤立をしてしまう危険もあります。
社会的に孤立をすると、認知症にもなりやすくなります。
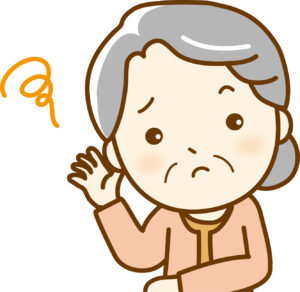
また、難聴と認知症には何らかの関わりがあるのかと題した、慶応義塾大学病院耳鼻咽喉科の先生と東京慈恵会医科大学精神医学講座の先生の対談を読んでみました。
その中で、2015年に厚生労働省が発表をした新オレンジプランにおいて、難聴は認知症の危険因子の1つとして挙げられております。
認知症の危険因子の1つである難聴は、様々な研究が進められておりますが、従来から行われている介入方法に補聴器の適切な活用があります。
ここでも言われていることですが、補聴器は眼鏡と同じようには使えないということです。
補聴器をつけることですぐに音がはっきりと聞こえるだろうと期待される人は多いけれども、音を聞き取るトレーニングが必要。
一般的には、補聴器をつけ始めてから少なくとも3か月~半年ほど定期的に通院をし、補聴器の音量などを調整しながら徐々に音を聞き取るトレーニングを続ける。
補聴器をつけたばかりの頃は雑音を含めて周囲の音が大きく聞こえるけれども、トレーニングを積むことで徐々にその中から必要な音や言葉を聞き取れるようになる。
補聴器の使用に当たり一定期間及ぶトレーニングは必要であることを知らないために、雑音が大きくなって、うるさいからと補聴器をつけなくなったり、耳になじまないと感じて補聴器を有効活用できないという人がいます。
なぜこのようなことが生まれるのでしょうか。

問題は、補聴器を販売する際に正しい情報提供が行われていないことです。
今や補聴器は家電量販店や眼鏡販売店、通販なども含め、様々な場所で購入できる時代になりました。
中には、売って終わりという販売店も存在をし、本来必要な正しい情報提供が行われないことや、定期的な聴力の経過観察や適切な補聴器の使い方の指導といった継続的なケアが行われないことも珍しくありません。
認定補聴器技能者が在籍をする補聴器の専門店であれば、正しい情報提供と継続的なケアが行われていると思います。
2018年より補聴器相談医が補聴器の診療情報提供書を作成をし、それを基に販売店で補聴器を調整する流れができ、さらに医療費控除が受けられるようになりました。
認知機能の低下により、今までできていたことができなくなり、家族から怒られたりして徐々に自信を失い、社会参加自体に消極的になっていく方が増えています。
適切な早期介入で認知機能の低下を抑えることができたらどんなにいいでしょうか。
まずは補聴器を購入した後になじむまでトレーニングが必要だということを知ってもらうために、市のほうから周知を行ってほしいと思いますけれども、いかがでしょうか、お伺いいたします。

◎健康・高齢部長・・・補聴器につきましては、ご指摘のとおり、購入してつければすぐに聞こえるようになるわけではなく、一定期間調整しながらトレーニングしていくことが必要であることは認識しております。
補聴器を購入しても調整やトレーニングをせず、適切な使用ができないまま補聴器を使用しなくなることは好ましくないと考えておりますので、購入費用の助成に当たりまして、その必要性の周知につきましては研究してまいりたいと考えております。
はしもと・・・補聴器は認知症予防にもつながります。毎年200万円前後の事業です。
どうかここで思い切って補聴器の購入費助成のコンセプトを変え、認知症の危険因子の1つとされている高齢者の難聴の早期発見と安心して購入できる体制づくりのためにとして、対象の拡大はもちろんですけれども、金額も上げてほしいと思います。
難聴や補聴器が必要かどうかを判断をする補聴器相談医の受診や、調整やアフターケアを行う販売店での購入などを費用助成の要件とするなど、医師会や専門家などと意見交換をし、市民の皆様が安心して補聴器を使い続けられるようにしていただくように、ここは要望とさせていただきますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
令和7年4月1日より、住民税所得割非課税世帯に限りますが、補助額が、3万円となっています。