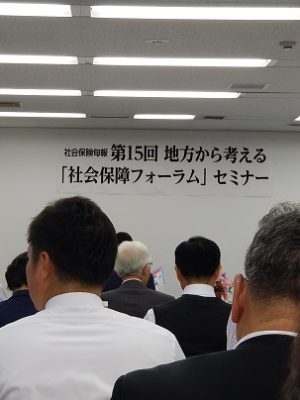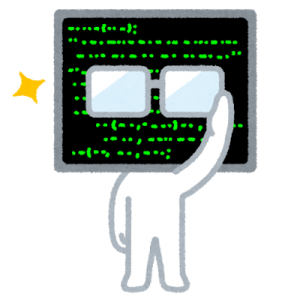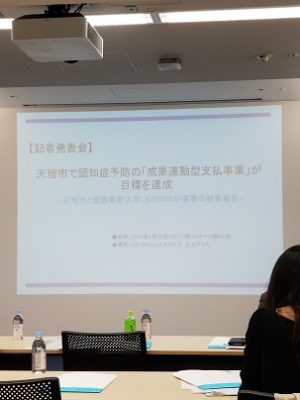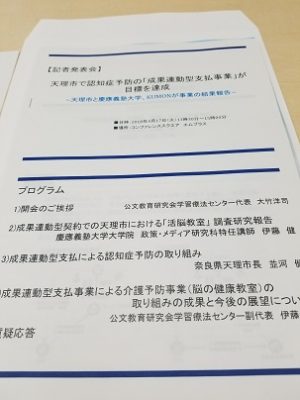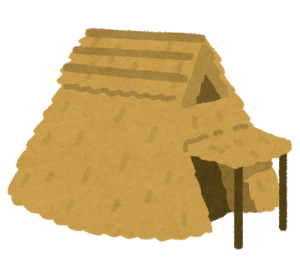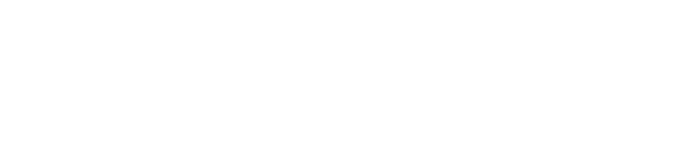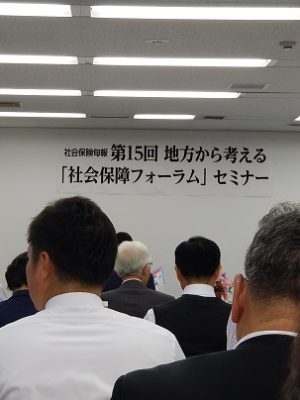
4月25日(水)ビジョンセンター東京有楽町で開催された「社会保障フォーラム」に参加しました。
講義1「平成30年度厚生労働省予算と地域共生社会への取組み」
厚生労働省 政策企画官より、「地域共生社会」の実現を目指して、今、直面している課題から話がありました。
人口推計から見えてくるもの、少子高齢化は、分かっていたものの、65歳以上の世帯構成が、30年前は、三世代が44.8%だったものが、今は、単独世帯が26.3%夫婦のみの世帯が31.5%と、明らかに、家族構成が変化していました。
また、生涯未婚率では、急速な上昇を続けています。これは、将来、高齢単身世帯となる可能性が高く、孤立化が懸念されます。
このような現実を直視しながら、「地域共生社会」これからの社会のかたちを考えなければなりません。
住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを送りたいと、誰もが思うものです。

しかし、暮らしが変化しています。例えば、認知症・精神疾患・がん・発達障害等、今は関係ないと思っていても、いつ、どこで、家族が、身内が、いづれ誰かがなったとしたら、他人事ではなくなります。このような事を念頭に置いて、こらからの社会のかたちを考えなければなりません。
箕面市・町田市・京田辺市などの実践例を通し、地域と連携し、高齢者や障害を持った方たちが、生き生きと働く様子や、地域の見守りなど、これからの在り方を考えさせられました。
講義2「市町村はデーターヘルスに如何に取り組むか」
厚生労働省 保険局国民健康保険課長より、市町村における予防・健康づくり対策はどう進めればよいか。そのために何が必要か。今後、現役世代が減少し後期高齢者が増大する中、特に留意すべきことは何か。話がありました。
生活習慣病は、死亡数割合では約6割を占め、一般診療医療費の約3割を占めています。
国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針「健康日本21(第二次)」の概要では、全ての国民が共に支えあい、健やかで心豊かに生活ができる活力ある社会の実現をめざし、具体的な取組が出されました。
医療機関のレセプト【患者が受けた保険診療について、医療機関が保険者(市町村や健康保険組合等)に請求する医療報酬の明細書の事】を電子化し、特定健診の結果も電子化し、これらの情報を活用することをデータヘルスと言います。このデーターをいかに活用するかが求められています。

展開例として、糖尿病性腎症重症化予防について話がありました。簡単に言うと、透析を受けると、高額な医療費がかかります。
発病予防のために、健康づくりや健診・保健指導などを行い、重症化を予防することにより、透析に至らないようにします。
市町村は地域の医師会等と連携・協働で取り組むことが必要です。健康寿命の延伸を目指しています。
講義3「生活困窮者自立支援制度の見直しと生活保護法の改正」
厚生労働省 大臣官房審議官より、生活困窮者自立支援制度・生活保護制度・すまいの確保支援・自殺防止総合対策など、話がありました。
生活困窮者等の一層の自立を支援するために、生活困窮者自立支援法や生活保護法・社会福祉法が見直しされていることを通し、新たな取り組みを教えてもらいました。
生活困窮者は、既に顕在化している場合と課題を抱えてはいるが見えにくい場合があるので、いかに、サービスにつなげるかが重要です。

例えば、生活支援課に相談をしても、生活保護に至らない人、ひきこもり状態にある人、離職期間が1年以上の長期失業者、スクールソーシャルワーカーが支援している子ども達、それぞれの状況に応じた支援をいかにつなげるかがこれからの課題です。
行政だけではなく、地域の支えあいが必要です。
生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るために、大学への進学を支援するための「進学準備給付金」が創設されます。
また、「健康管理支援事業」を通し、生活習慣病が発見されても医療機関にかからない人や治療を中断した人が放置することによる、重篤な合併症を発症するリスクを抑えたり、ジェネリック医薬品の使用を原則化するなど、医療費削減に取り組みます。

ジェネリック医薬品の使用について、数年前に取り上げたことがありますが、強制力がありませんでしたので、新薬でも後発薬でもどちらでも良かったため、医療扶助費の削減には至りませんでしたが、今回、原則化となったことは大きな意味があると思います。
社会が多様化する中で、地域生活の現場で起きる問題は複雑化・複合化しています。これらが最も深刻化した時に、自殺が起きると言われていますので、どうしたら、命を自ら断つようなことがなくなるのか、考えて参ります。
厚生労働省が考えている事が良く分かりました。これらが机上の議論に終わらないように、現場でしっかりと取り組んで参ります。